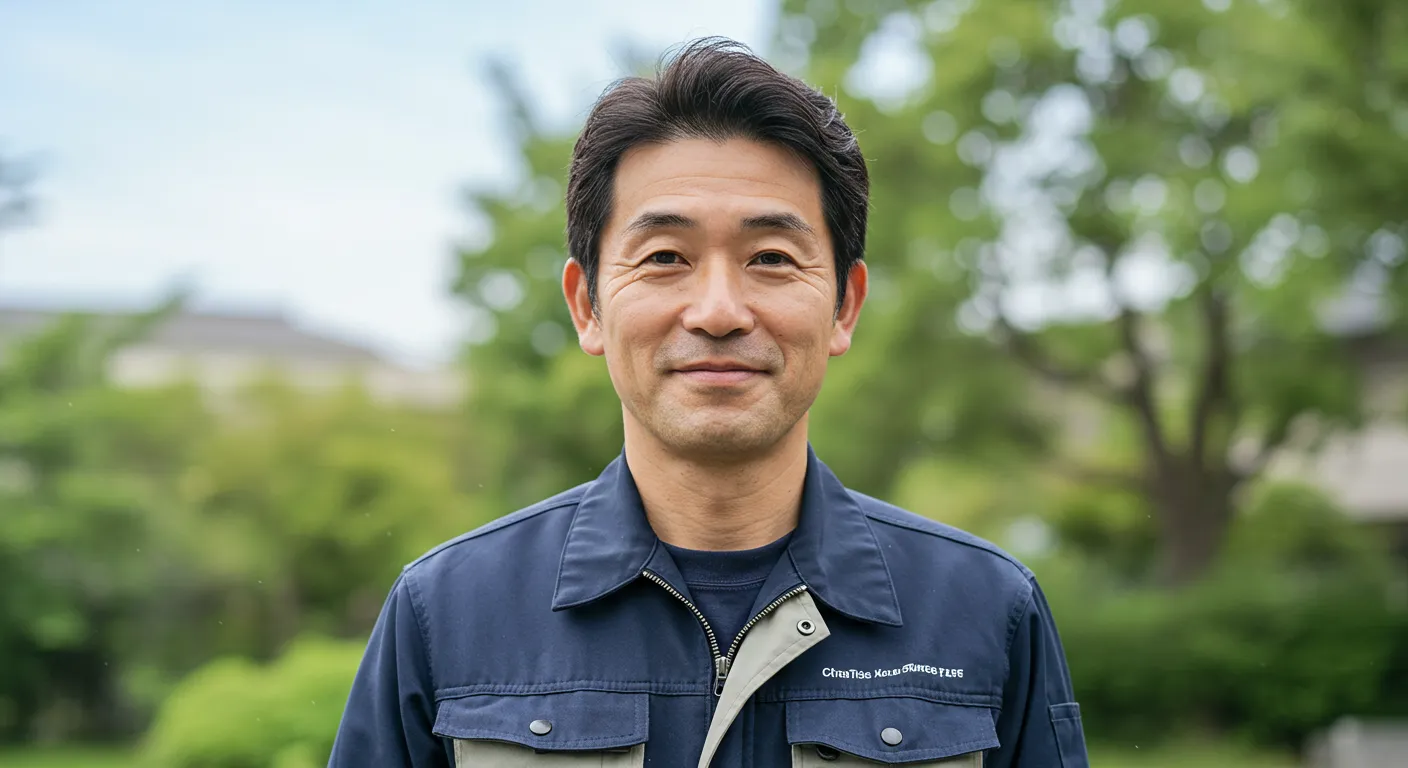※本記事にはプロモーションが含まれています
「最近、夜になると天井裏からバサバサと羽音が聞こえる…」
「換気扇の下やベランダに、黒くて細長いフンが毎日落ちている…」
その不気味なサインの正体は、あなたの家に住み着いたコウモリかもしれません。
たかがコウモリと侮ってはいけません。騒音や悪臭を放つフン害はもちろんのこと、そのフンを介したアレルギーや、狂犬病ウイルス、ヒストプラズマ症といった深刻な感染症のリスクも。放置は絶対に禁物です。
しかし、いざ駆除しようにも「どうやって?」「そもそも自分でやってもいいの?」と疑問だらけですよね。
この記事では「法律の遵守」「安全な作業」「完全な再侵入防止」を3つのキーワードに、コウモリ駆除の正しい知識と手順を、初心者の方にもわかるように一から丁寧に解説します。
業者に頼むべきか、自分でできるのか。その費用とリスクを比較し、あなたが今取るべき最善の行動がはっきりと見えてくるはずです。
1. コウモリ被害のサインと放置してはいけない健康リスク
まず、あなたの家で起きていることが本当にコウモリによるものなのか、そのサインをチェックしましょう。
- フンによる被害: 家の壁、ベランダ、換気口の真下などに、1cm程度の黒くて細長く、パサパサしたフンが散らばっている。ネズミのフンと似ていますが、コウモリのフンは昆虫が主食のため、指でつまむと簡単に崩れるのが特徴です。
- 騒音: 日が暮れる夕方から夜中にかけて、天井裏や壁の中から「バサバサ」「ガサガサ」という羽音や、「キーキー」「キュルキュル」といった甲高い鳴き声が聞こえる。
- 目視: 夕暮れ時に、家の軒先や屋根の隙間、通気口などからコウモリが飛び立っていくのを見る。
これらのサインに心当たりがあれば、コウモリが住み着いている可能性が非常に高いです。そして、それを放置することには、想像以上の危険が潜んでいます。
| 被害の種類 | 具体的なリスク内容 |
| 健康被害(感染症) | 狂犬病やヒストプラズマ症など、海外では死亡例もある感染症を媒介する可能性があります。直接触れるのはもちろん、乾燥したフンを吸い込むだけでも感染リスクがあり、特に免疫力の低い子どもや高齢者がいるご家庭は注意が必要です。 |
| 衛生被害(フン・尿) | 同じ場所に大量のフンをする習性があるため、天井裏がフンだらけに。強烈な悪臭を放つだけでなく、天井のシミや腐食の原因になります。また、ダニやノミといった害虫の発生源にもなります。 |
| 精神的・経済的被害 | 夜間の騒音による睡眠不足やストレス。建材の腐食による修繕費など、被害が拡大すればするほど経済的な負担も大きくなります。 |
2. 駆除前に必ず確認!鳥獣保護法と自治体への許可申請
コウモリ駆除を考える上で、絶対に知っておかなければならない大原則があります。それは、コウモリは「鳥獣保護管理法」という法律で保護されているということです。
これを無視して自己流で駆除を行うと、法律違反となり【1年以下の懲役または100万円以下の罰金】が科される可能性があります。
コウモリ駆除で「やってはいけないこと」
- 許可なく捕獲すること
- 殺傷すること(毒エサなどを含む)
- 巣の中にヒナがいる状態で、親を追い出して巣の入口を塞ぐこと
コウモリ駆除で「やるべきこと」
法律を守った正しい駆除とは、コウモリを傷つけずに「家から追い出し、二度と入ってこられないように侵入口を塞ぐ」ことです。これが唯一の合法的な対策となります。
万が一、どうしても捕獲が必要な特殊なケースでは、必ずお住まいの市役所や町村役場といった自治体に相談し、「捕獲許可」を申請する必要があります。しかし、この許可が下りることは稀であり、基本は「追い出しと侵入口封鎖」であると覚えておいてください。
3. 駆除ステップ3段階(追い出し▶忌避▶侵入口封鎖)
安全で合法的なコウモリ駆除は、以下の3つのステップで進めるのが基本です。
ステップ①:追い出し
まずは家の中にいるコウモリを、すべて外に追い出すことから始めます。
- タイミング: コウモリがエサを探しに外へ出ていく日没後の数時間がベストタイミングです。
- 方法:
- 燻煙(くんえん)タイプの忌避剤: 天井裏などで使用し、煙の力で一気に追い出します。火災報知器に反応しないよう、カバーをかけるなどの注意が必要です。
- 忌避スプレー: コウモリが潜む隙間に直接噴射し、嫌なニオイで追い立てます。ハッカ油を主成分としたものが一般的です。
- 強い光や音: CDやアルミホイルを吊るして光を乱反射させたり、超音波発生器を使ったりする方法もありますが、効果は限定的です。
【重要】繁殖期(6月~8月頃)の追い出しは避ける
この時期は、巣の中にまだ飛べない赤ちゃんがいる可能性があります。この状態で親を追い出して入口を塞いでしまうと、子どもが中で死んでしまい、死骸が腐敗するだけでなく、鳥獣保護法に抵触する恐れもあります。
ステップ②:忌避
コウモリを追い出した後、戻ってこないように「ここは居心地が悪い場所だ」と認識させます。
- 方法:
- コウモリが巣にしていた場所や、出入り口になっていた隙間に、ジェルタイプやスプレータイプの忌避剤を塗布・散布します。
- 忌避剤にはコウモリが嫌うハッカやナフタレン系の成分が含まれており、一定期間コウモリを寄せ付けない効果が期待できます。
ただし、忌避剤の効果は永続的ではありません。これはあくまで一時的な対策であり、次のステップ③が最も重要になります。
ステップ③:侵入口封鎖
コウモリ駆除の成否は、このステップにかかっていると言っても過言ではありません。
コウモリ(特にアブラコウモリ)は、わずか1~2cmの本当に小さな隙間からでも侵入できてしまいます。考えられる侵入口をすべて特定し、物理的に塞ぐ必要があります。
- 主な侵入口の例:
- 屋根瓦の隙間
- 壁と屋根の間の隙間(軒先)
- 換気口、通気口
- 壁のひび割れ、サイディングの継ぎ目
- エアコンの配管導入部の隙間
- シャッターの戸袋
- 封鎖に使う資材:
- 金網、パンチングメタル: 目の細かいもの(1cm以下が必須)で通気口などを覆います。ステンレス製が錆びにくくおすすめです。
- シーリング材(コーキング剤): 壁のひび割れなどの小さな隙間を埋めます。
- パテ: 配管周りなどの複雑な形の隙間を埋めるのに便利です。
プロのテクニック: すべてのコウモリが家から出て行ったことを確認するまで、出口を一つだけ残しておきます。数日間、フンが増えていないかなどを確認し、完全に出て行ったと確信できてから、最後の出口を塞ぎます。
4. DIY vs 業者:費用・安全性・再発率を徹底比較
「これなら自分でもできるかも?」と考える方もいるでしょう。しかし、DIYと専門業者への依頼には、それぞれ大きなメリットとデメリットが存在します。
| 比較項目 | DIY(自分で駆除) | 専門業者 |
| 費用 | ◎ 5,000円~3万円程度 (資材購入費のみ) | △ 3万円~20万円以上 (被害状況や建物の構造による) |
| 安全性 | × 危険 (高所からの転落や感染症のリスク) | ◎ 安全 (専門装備と感染症対策が万全) |
| 確実性・再発率 | △ 不確実 (侵入口の見落としで再発率が高い。保証なし) | ◎ 確実 (専門知識で完全封鎖。再発保証付きが多い) |
| 法的リスク | △ あり (誤って法律違反を犯す可能性) | ◎ なし (法律を遵守した正しい手順で実施) |
| 手間・時間 | × かかる (侵入口の特定やフンの清掃に多大な時間) | ◎ 早い (専門家が迅速に対応) |
【結論】
費用を抑えられるのがDIYの唯一のメリットですが、高所作業の危険性、感染症のリスク、そして何より再発率の高さを考えると、専門業者に依頼するのが最も安全かつ確実な方法と言えます。特に、被害が広範囲に及んでいる場合や、2階以上の高所に侵入口がある場合は、迷わずプロに相談しましょう。
5. 再侵入を防ぐメンテナンス
業者に依頼した場合でも、自分で対策した場合でも、再発を防ぐための定期的なチェックは欠かせません。コウモリは非常に執着心が強く、一度住み着いた場所に戻ろうとする習性があります。
- シーリング材(コーキング剤)のチェック: 耐用年数は約5~10年です。経年劣化でひび割れや剥がれが生じると、そこが新たな侵入口になります。年に一度は外壁をチェックしましょう。
- 金網やネットのチェック: 強風でずれたり、何かの拍子で破れたりしていないか確認しましょう。
- 家の周りの環境整備: コウモリのエサとなる昆虫が集まらないよう、庭の草むしりをしたり、屋外の照明をLEDに変えたりすることも間接的な対策になります。
- 超音波装置について: コウモリが嫌がる超音波を発生させる装置ですが、専門家の間でも効果は賛否両論です。コウモリが音に慣れてしまうケースも多く、これ単体での根本解決は難しいと考え、あくまで補助的なものと認識しておきましょう。
6. おすすめ忌避剤&防獣ネットの種類
DIYで対策する場合、どのような製品を選べばよいのでしょうか。
忌避剤の種類
- スプレータイプ: 即効性が高く、コウモリが潜んでいる場所に直接噴射して追い出すのに適しています。ただし、効果の持続時間は短いのがデメリットです。
- ジェルタイプ: 雨風に強く、効果が1ヶ月以上持続する製品もあります。侵入口や巣があった場所に塗布し、コウモリを寄せ付けない環境を作るのに使います。
- 燻煙タイプ: 天井裏など、密閉された広い空間に煙を充満させて一気に追い出すのに強力な効果を発揮します。使用時は火気厳禁です。
侵入防止ネット
- 素材: 屋外で使うため、耐久性の高いポリエチレン製や、より頑丈なステンレス製がおすすめです。
- 目合い(網目の大きさ): これが最も重要です。必ず目合いが1cm(10mm)以下のものを選んでください。 これより大きいと、コウモリは簡単に通り抜けてしまいます。
- 色: 黒やグレー、シルバーなどが一般的です。外壁の色に合わせて選ぶと目立ちにくくなります。
7. よくある質問(FAQ)
Q1. コウモリ駆除に最適なシーズンはいつですか?
A1. コウモリが活動的で、かつ繁殖期ではない春(4月~5月)と、子育てが終わり冬眠に入る前の秋(9月~10月)が最も適しています。繁殖期の夏(6月~8月)は、巣に飛べない子どもが取り残され、中で死んでしまうリスクがあるため絶対に避けるべきです。
Q2. 天井裏に溜まったフンはどうやって掃除すればいいですか?
A2. 完全防備で行う必要があります。高性能な防塵マスク(N95規格推奨)、ゴーグル、ゴム手袋、使い捨ての作業着を着用してください。乾燥したフンは菌が飛散しやすいため、消毒用エタノールなどを霧吹きで少し湿らせてから、静かにホウキとチリトリで集めます。集めたフンは袋を二重にして密閉し、可燃ゴミとして捨てます。最後に、フンがあった場所を再度エタノールで消毒します。ただし、健康リスクが非常に高いため、フンの清掃・消毒は専門業者に依頼することを強く推奨します。
Q3. 駆除費用に火災保険は使えますか?
A3. 一般的に、コウモリなどの害獣が原因のフン害や建物の汚損そのものには、保険が適用されないケースがほとんどです。 これは「経年劣化」や「予測可能な被害」と見なされるためです。ただし、コウモリが配線をかじった結果、漏電や火災が発生した、といった二次被害に対しては、契約内容によって保険が適用される可能性があります。まずはご自身の加入している保険会社に問い合わせてみましょう。
8. まとめ|コウモリ駆除で後悔しないために
最後に、コウモリ駆除で失敗しないためのポイントをまとめます。
コウモリ駆除まとめ
- コウモリは鳥獣保護管理法で保護されているため、許可なく殺したり捕まえたりしてはならない。
- 駆除の基本は、「追い出し → 忌避 → 侵入口の封鎖」の3ステップ。
- 健康被害のリスクがあるため、フンなどを扱う際は完全防備で行う。
- 再発防止のためには、1cm程度の隙間も見逃さず、徹底的に塞ぐことが最も重要。
- DIYは危険と再発リスクが伴うため、安全と確実性を求めるなら専門業者への依頼が最善の選択肢。
優良な専門業者の見つけ方
もし業者に依頼すると決めたら、以下のポイントで業者を選びましょう。
- 複数の業者から見積もりを取る(相見積もり)。
- 見積書の内訳が明確か(作業内容、使用する資材、出張費など)。
- 作業前に現地調査をしっかり行ってくれるか。
- 駆除後の「再発保証」があるか。
- これまでの実績や口コミ評価はどうか。
コウモリ被害は、放置していても絶対に解決しません。この記事を参考に、あなたの状況に合った正しい一歩を踏み出し、一日も早く安全で安心な日常を取り戻してください。